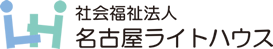アイのかけはし vol.108ai
創立80周年連動企画『施設長リレーインタビュ―』
みなさまのおかげさまをもちまして、社会福祉法人名古屋ライトハウスは2026年10月、創立80周年を迎えます。
法人情報誌である「アイのかけはし」では、これを機に7名の現施設長のお考えや人となりに迫るべくリレーインタビューを敢行し、社会福祉法人名古屋ライトハウスの現在地をみなさんとともに眺めてみたいと思っています。
第2回目となる今回は、名古屋ライトハウス情報文化センター 岩間康治さんです。
~岩間康治さんプロフィール~
一般企業で測量業務に従事していた1997年12月頃、目の不調を感じる。
1998年1月 レーベル病と診断。失明。
1999年2月~2000年3月 名古屋市総合リハビリテーションセンターにて点字の読み書き等を学ぶ
2002年3月 名古屋ライトハウス情報文化センター(当時の名称は名古屋盲人情報文化センター) アルバイト入社。点字出版事業部配属。
2004年4月 社員登用。点字出版事業部。
2013年4月 サービス事業部へ。
2016年4月 光和寮へ異動。視覚障害者支援室。
2018年4月 名古屋ライトハウス情報文化センターへ移動。サービス事業部。
2019年10月 同 所長就任。現在に至る。

情報文化センターは視覚障害者情報提供施設です。岩間さんは12代目の施設長として、ご利用者への情報提供をはじめ、さまざまな視覚障害者支援を届かせるべく、職員とともに日々奮闘しています。本インタビューでは、岩間さんの中途失明後のことから施設運営における信念、今後の展望について深く掘り下げていきます。
Q: 岩間所長、本日はよろしくお願いいたします。インタビュアーは情報文化センター寺西善彦が努めます。まずは、福祉の世界を志したきっかけ、ライトハウスに入職したきっかけを教えていただけますか。
私は、26歳の時にレーベル病を発症し失明しました。当時は測量の仕事に就いていたのですが、医師からは新しい仕事を探すよう言われました。見えなくなってしまうということが本当にショックで、半年位は引きこもりのような状態になり、とても仕事探しなど出来ませんでした。それでも少しずつ見えないことを受け入れていき、名古屋市総合リハビリテーションセンターで点字の読み書きの訓練と音声ガイド(スクリーンリーダー)のパソコン訓練を受けるようになりました。家に居ても、寝る間も惜しんでと言ってもいいくらい、とにかく点字やパソコンの訓練を続け、だいぶ習得した頃に当時の盲人情報文化センターでアルバイトを募集しているのを見つけて応募し採用いただきました。つまり、福祉の世界に入ったきっかけは、自分が見えなくなったことですね。
Q: 中途失明という人生の一大事から、情報文化センターにアルバイト入職し現在では施設長になられていらっしゃるわけですが、30代、40代、50代とそれぞれの配属先と当時の思い出などをお聞かせいただけますか?
まずは、最初に配属された点字出版事業部で11年勤務しました。広報なごや、広報とよたなどの製作や、図書館の点字蔵書データ化、全国への貸し出しに携わりました。その後、センター内で異動があり、サービス事業部で5年間勤務しました。相談業務、ICT、日常生活用具や歩行補助具の知識習得、利用者への情報伝達を行いました。入職時に既に30歳だったので、ここまでで40代半ばになっています(笑)。その頃、法人本部で視覚障害者支援室が設立され異動。2年間勤務しました。ここでは情報発信・提供に注力し、医療機関(病院、眼科)とのネットワーク構築、愛知県眼科医会のスマートサイトあいち製作、中間型アウトリーチ(眼科での患者相談対応)に注力しました。

Q: 施設長になられたきっかけといいますか、打診のようなものはあったのですか?
視覚障害者支援室の2年目に、当時のセンターの施設長から打診というかお話しをいただいたのを覚えています。取り組んでいた医療連携の仕事にやりがいを感じていたこともあり、大変迷いましたが、当時のセンターにも素晴らしい職員、ボランティアの方々が揃っていたこと、情報文化センターに充実した情報発信機能を持たせ、当事者の情報収集に役立てたいという強い思いが自分にあったことなどから、お引き受けする気持ちになっていきました。
私自身が失明の診断を受けた時、なにをどうしたらよいのか、まるで情報が無い。あったのだろうけど、わかりづらかった。振り返ればそれが私の原点のようなものであり、あの時の自分に届くような情報発信を実現したいという気持ちが、特に強くありました。
Q: 施設長になられたことで、ご自身の経験から感じられたことを、施設運営につなげていけるっていうのはありますか?
それはありますね。さまざまな形でのセンターとしての情報発信の充実を目指すことはもちろんですが、個人的にもやりがいを感じ、必要だと思っていた医療連携強化も継続し取り組み、現在は眼科三宅病院、眼科杉田病院でロービジョン外来相談を担当しています。
Q: 医療機関との連携強化や、情報が届きにくい方々へのアプローチについて、もう少し詳しくお伺いしたいです。
「ここに情報文化センターがある」といったような基本的な情報が届く人と届かない人がいらっしゃいます。見えない、見えづらいすべての方々にきちんと情報を届かせるためのひとつとして医療との連携強化を進めています。患者さんとして訪れる見えづらくなった方々への情報提供のみならず、医師や視能訓練士の方々にも知ってもらう必要もあると考え、愛知県眼科医会の広報誌にロービジョンラボのコラムを執筆しています。
また、視覚障害者支援と言っても、先天性、後天性、年齢、個人の感覚など、人によって状況が異なります。そのそれぞれの人に対応できる事業やサービスを進める必要があるため、いまでは、名古屋ライトハウス情報文化センター、名古屋市総合リハビリテーションセンター、名古屋盲学校と連携し定期的に勉強研究会を開催するなど情報共有を行うようになっています。

Q: 現在の情報文化センターの強みはなんでしょうか?
いろいろありますが、現在の職員27名のうちの3分の1、私を含めて9名が視覚障害当事者職員であることは強みのひとつと言えると思います。
Q: 視覚障害当事者職員の強みとは何でしょうか?それはどのように活かされていますか?
情報文化センターの職員であることの前に、視覚障害当事者として一人ひとりが意見を持ち、それぞれが多様なネットワークを通じて、自身も含めた利用者の声として発信が出来る。当事者であるからこそのリアリティがあります。これは強みです。
また、9名いるということも大きく、仕事においてもそれぞれ担当業務に違いがある。業務によって利用者対応も変わりますので、より多様な当事者の声を受け止めることが出来る。そういった強みは、晴眼の職員と連携することで、大きな意味を持ってきます。
視覚障害者への理解に基づき、それぞれが協力しながら且つそれぞれの持ち場で力を発揮しているからこそ、偏った情報が伝わるのを防ぎ、幅広い視点での支援を可能にしています。この相互作用こそが本当の強みだと思っています。
Q: 情報の受信と発信ともに大きく関わる点字についてはどうお考えですか。
私の経験でお話しすると、リハビリセンターでの点字勉強を始めたころは、指先で読み取るのが難しく、形を覚えるのも大変でした。悔しくて、1日中触って練習し、指先が痺れるほどでした。1週間ほどで五十音を覚えて触れるようになり、それが大きな自信となりました。何もできないと思っていたので、点字を習得できたことは自信となり、その後のパソコン(ワード、エクセル、メール作成)の勉強にも繋がりました。
点字の習得は、生きる力を得たような感覚で、自分が立ち直る大きなきっかけとなりました。当施設に入職した際も点字出版事業部で良かったと思っています。

Q:今後のセンターをどのような場所にしていかれたいですか?
これまでは視覚障害者への情報提供が主な役割でしたが、今後は、それだけではなく、今まで以上に地域の方々への認知度向上が重要と考えています。地域の方々にセンターを知ってもらうことで、視覚障害者に情報が届く。そのようなことも施設の存在意義を高めることになりますし、そういった取り組みを強化していく必要があります。
また、引き続き利用者の声を聞き、それに応えることも大切なミッションです。情報が届かないことによる不安を解消するため、この施設だけでなく福祉制度なども含め、様々な情報を伝えることで不安を和らげること。そのような場所にしていきたいですし、それが情報提供施設の役割だと考えています。
Q:これからの読書環境はどうなっていくと思いますか?
読書環境はこれからも変化していくと思います。私たちはセンター名称を2020年に「名古屋盲人情報文化センター」から「名古屋ライトハウス情報文化センター」に変更しましたが、これは視覚障害者だけでなく、様々な方々に利用してもらえる施設にしていきたいという思いがあっての変更でした。
2019年に読書バリアフリー法が施行され、視覚障害者だけでなく、識字障害や読字障害の方々、肢体不自由(本のページをめくるのが難しい)の方々にも図書を楽しんでいただける環境が整ってきました。音声図書はそういった皆さんにご利用いただくことが出来ます。以前は障害者手帳の有無でセンターのご利用は区切られていましたが、今は手帳が交付されない眼球運動困難者の方などもいらっしゃいます。少しずつ制度が柔軟になってきていますので、センターが枠組みを作るのではなく、枠組みを取り払い、利用出来るサービスがあることを世の中に広く知ってもらい、必要とする方々に本当に使ってもらえる施設であることにより、よりよい読書環境を一緒に作っていけたらと思います。私たちが時代に合わせて変化していくことで、読書環境も変わっていくものと思います。
Q:では最後に、情報文化センターの職員、あるいは法人全体の職員に向けて、メッセージや期待されることがあればお聞かせいただけますでしょうか?
情報文化センターの職員に対しては、私が2019年10月に所長に就任して以来伝えてきた方針を踏まえ、一人ひとりの職員が自身の考えを大切にしてほしいということを改めて伝えたいです。それぞれのこれまでの経験と私の伝えてきたことを踏まえ、自分だったらどうしていきたいかを考えてほしいと思います。
法人全体としては、情報文化センターは視覚障害支援に特化している部分がありますが、障害の有無に関わらず、一人ひとりのパーソナリティを尊重し、利用者の「生きがい」や前向きなものを大切にして支援に当たってほしいです。そのためにも、利用者の声を聞き取る力、それをどう実現していくかを職員一人ひとりが考え、叶えていく努力をしてほしいです。

本日はありがとうございました。